木下杢太郎について(3) 医学者・太田正雄
医学者としての評価

東北帝国大学教授時代
文学界では「木下杢太郎」の名で知られる杢太郎ですが、医学の世界では本名の「太田正雄」で知られています。
太田正雄は東京帝国大学を卒業後、土肥慶蔵教授の皮膚科学教室に入り、大正5(1916)年、31歳の若さで南満医学堂教授として奉天(現在の中華人民共和国遼寧省瀋陽市)に赴任しました。この頃から真菌の研究に打ち込み、水虫の原因が白癬菌であることを日本で初めて特定しました。
その後、大正10年から13年にかけてフランスに留学し、太田-ランゲロン分類と呼ばれる真菌の分類法を確立。その功績が認められ、後年、フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章を授与されています。
フランスから帰国した後には愛知医科大学(現在の名古屋大学医学部の前身)や東北帝国大学の教授を歴任し、昭和12(1937)年に52歳で東京帝国大学医学部教授に就任しました。この頃にはハンセン病の研究を行なうため、熱心に伝染病研究所に通っていました。
その他の主な業績としては、眼上顎部褐青色母斑という顔にあざができる病気を発見したので、現在この病気は全世界で太田母斑と呼ばれています。
このように、皮膚科学の中でも様々な活躍をした太田正雄は、日本のみならず世界的にも偉大な医学者といえるでしょう。
太田正雄とハンセン病

伝染病研究所にて:矢印が杢太郎
ハンセン病は、らい菌に感染することによって起こる感染症です。ただし、感染力は非常に弱く、通常はほとんど感染しません。また、感染しても発病することはまれで、現在では適切な治療を行なえば確実に治る病気です。
ハンセン病は発症すると末梢神経がマヒしたり、皮膚に発疹など様々な症状が現れたりします。また、手足や顔など体の一部が変形する後遺症が残ることもあり、患者は世界的に長く差別され、隔離されてきました。特に、日本においては治療法が確立された後にも「らい予防法」によって強制隔離が続けられ、平成8(1996)年に「らい予防法」が廃止された今も差別と偏見に苦しむ患者の方々がいます。
太田正雄がハンセン病研究に取り組んでいた頃、ハンセン病はまだ治療法が確立されておらず、不治の病とされ、患者は強制的に隔離されていました。しかし、太田正雄はこの病気を可治の病と考え、症状の程度にもよるが基本的に隔離は不要と唱えました。そして、実際にハンセン病の治療法を開発するため、伝染病研究所においてらい菌の培養および動物接種実験を繰り返しました。しかし、らい菌の培養は非常に難しく、現在でも人工培地では成功していません。太田正雄はこの困難な実験をあきらめることなく続けましたが、昭和20(1945)年、治療法の確立を見ることなく60歳で亡くなりました。
木下杢太郎について
伊東市立木下杢太郎記念館
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1961~1964
生涯学習課へメールを送信する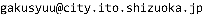










更新日:2019年07月02日