国民健康保険
国民健康保険とは
私たちは、家族がみんな健康で幸福な家庭を願っています。しかし病気やケガは、突然におそってくることが多いものです。国民健康保険(以下国保という。)は、このような不時の出費(医療費)に対し、あらかじめみんなでお金を出し合って出費に備えるという助け合いを目的とした保険です。
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護を必要としている高齢者の急増に対し、家族だけで介護することが難しくなっています。
そこでこうした介護を社会全体で支える「介護保険制度」が2000年4月1日からスタートしました。この制度では、65歳以上の人を介護保険第1号被保険者とし、40歳以上65歳未満の人を介護保険第2号被保険者としており、国保に加入している世帯で40歳以上65歳未満の人がいる世帯の世帯主は、介護納付金課税額として、従来の医療費分に加え国民健康保険税を納めることとなります。
また、2008年4月1日からは後期高齢者医療制度が始まり、この制度を支えるための後期高齢者支援金等課税額が加わりました。
したがって、国保は介護保険制度及び後期高齢者医療制度を財政面から支える制度でもあります。
2018年4月から、国民健康保険制度が変わりました。詳しくは下記のファイルをご覧ください。
国民健康保険制度が変わります (PDFファイル: 351.5KB)
国保に加入するとき・やめるとき(14日以内に届け出ましょう。)
国民健康保険の加入・喪失手続に関するお願い
2017年11月13日から、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されました。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
国民健康保険資格の取得・喪失の手続についても、情報連携は行われ、これまで必要とされてきた添付書類(資格喪失証明書など)の省略が可能になりました。
しかし、情報連携は、連携対象となる情報を情報提供者が登録した後、一定期間を要する場合があり、情報連携ができるまで相当の日数を要するなどの問題が想定されます。
また、添付書類の省略が可能な場合も、一部の健康保険組合等において、情報連携ができない状況になっており(添付書類省略困難保険者)、添付書類の省略ができない扱いとなっています。
伊東市国民健康保険のお手続に関しては、本格運用後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続内容に応じた添付書類の提出をお願いします。
添付書類省略保険者リストは次のリンクをご覧ください。
| こんなとき | 手続のやり方 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 職場の健康保険などに加入していない人が、他の市区町村から転入してきたとき | 市民課又は出張所の窓口で転入の届出に併せて国民健康保険資格の取得の手続を行ってください。 |
|
| 職場の健康保険をやめたとき・被扶養者からはずれたとき | 市民課又は出張所の窓口で国民健康保険資格の取得の手続を行ってください。 |
|
| 子どもが生まれたとき | 市民課又は出張所の窓口で出生の届出に併せて国民健康保険資格の取得の手続を行ってください。 |
|
| 生活保護を受けなくなったとき | 国民健康保険資格の取得について、担当ケースワーカーにお尋ねください。 |
|
外国籍の人(一部の在留目的の人を除きます。)が、職場の健康保険などに加入せず、3か月を超えて日本に滞在するときも国民健康保険に加入しなければなりません。
- (注釈1)国民健康保険に加入すると、その世帯主に国民健康保険税が賦課されることになります。伊東市では、2017年1月1日から国民健康保険税は原則的に口座振替で納めていただくことになりました。ご利用いただける金融機関が限られておりますのでご注意ください。
- (注釈2)ペイジー口座振替受付サービスとは、専用の端末にキャッシュカードを通すことで、(注釈1)の口座振替をよりお手軽に、銀行の印鑑なしでお申込みできるサービスです。市役所保険年金課と収納課でご登録いただけます。なお、ペイジー口座振替受付サービスは、一部の金融機関に対応しておりません。
| こんなとき | 手続のやり方 | その他の持ち物 |
|---|---|---|
| 他の市区町村に転出するとき | 市民課又は出張所の窓口で転出の届出に併せて国保資格の喪失の手続を行ってください。 |
|
| 職場の健康保険に加入したとき・被扶養者となったとき | 市民課、出張所の窓口又はオンライン申請で国保資格の喪失の手続を行ってください。 |
|
| 国保の被保険者が死亡したとき | 市民課又は出張所の窓口で死亡の届出をすると国保資格を喪失します。 |
|
| 生活保護を受け始めたとき | 国民健康保険資格の喪失について、担当のケースワーカーにお尋ねください。 |
|
| 後期高齢者医療制度に移行したとき | 75歳になって後期高齢者医療制度に移行するときは届出は不要です。 |
|
上記の手続に共通する持ち物
- 身元確認書類
マイナンバーカード等の官公署発行の写真付証明書 - マイナンバーがわかるもの
- 市役所に返納する以下のもの
- 国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ
- 国民健康保険限度額適用認定証
- 国民健康保険特定疾病療養受療証 など
保険税は
みなさんの医療費、介護納付金や後期高齢者支援金等に充てられる国保財政の重要な財源です。必ず納期限までに納付してください。
保険税は、毎年4月1日現在でその年の保険税の額を決定し、納税通知書により税額、算出方法、納期限、納入場所などを通知しています。納税には直接納入されるほかに、口座振替による納入方法もありますので、ご利用ください。
また、65歳から74歳の方で構成されている世帯については、年金からの特別徴収となります。
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)と介護納付金課税額と後期高齢者支援金等課税額の3本立て課税になります。
賦課限度額は、基礎課税額(医療分)は65万円、後期高齢者支援金等課税額は24万円、介護納付金課税額は17万円となります。なお、平成30年度賦課分から資産割が廃止となりました。
年間保険税は、次の表により計算されます。
| 区分 | 基礎課税額 (医療分) |
後期高齢者 支援金等課税額 |
介護納付金 課税額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 所得割 | 基準総所得金額にかかる割合 | 5.7% | 2.2% | 1.7% |
| 2 均等割 | 被保険者1人あたりの額 | 24,000円 | 9,600円 | 13,200円 |
| 3 平等割 | 1世帯あたりの額 | 16,000円 | 6,000円 | なし |
| 賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | |
1から3の合計額が1年間の保険税となります。
所得の少ない世帯は負担が軽減されます。
世帯主(擬制世帯主を含む。)と国保被保険者と国保から後期高齢者医療へ移行された方の総所得金額等(注釈1)の合計金額が一定基準以下の場合は、上表の2 均等割と3 平等割が軽減されます。
| 上記の所得合計金額が… | 軽減割合 |
|---|---|
|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の場合 |
7割 |
|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30万5千円×加入者:注釈2)以下の場合 |
5割 |
|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×加入者:注釈2)以下の場合 |
2割 |
- (注釈1) 昭和35年1月1日以前生まれの方の公的年金等に係る所得は、15万円を差し引いた金額で判定します。また、専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で判定します。
- (注釈2) 国保被保険者(擬制世帯主は除く。)と国保から後期高齢者医療へ移行された方も加入者へ含めて計算します。
- (注釈3)上記の表は、令和7年度以降の賦課分です。
- (注釈4)収入や所得がない方は住民税申告でその旨を申告することで軽減の対象となります。
未就学児の均等割額の減額
未就学児(小学校入学前までのお子様)の均等割額が2分の1減額されます。所得の少ない世帯の軽減に該当する世帯では、軽減後の均等割額から2分の1減額されます。
後期高齢者医療への移行に伴う保険税の緩和措置
後期高齢者医療へ移行されたため、国保世帯が単身世帯となったときは、5年間(世帯主と世帯員の関係が維持されている場合)は平等割額が2分の1になります。さらに、5年経過後の3年間は平等割額の4分の1を減額します。
減免について
国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が特別な事情により、その生活が著しく困難となり国民健康保険税の減免が必要と認められるときは、申請により基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額を減免します。
減免の条件、割合等はそれぞれの事由により異なりますので、保険年金課国民健康保険係へお尋ねください。
給付について
病気や怪我で医療機関にかかるとき、窓口に保険証を提示することで医療費の一部(2割~3割)を自己負担し、残り(7割~8割)を国保が負担します。
| 年齢 | 自己負担割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6歳未満 | 2割 | ||||||||
| 6歳以上70歳未満 | 3割 | ||||||||
| 70歳以上75歳未満 | 2割~3割 生年月日や所得に応じて変わります。詳しくは下記「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について」のとおり。 |
療養費
コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)、申請に基づいて国保の基準により7割~8割を支給します。
【申請に必要なもの】
1.国民健康保険療養費支給申請書(下記の添付ファイルをご覧ください)
2.請求兼領収書(下記の添付ファイルをご覧ください)
3.領収書および内訳書(領収書に内訳が記載されていれば不要)
4.医師の診断書・意見書等
5.マイナンバーカード・資格確認書・保険証いずれか一点
6.世帯主の口座番号のわかるもの
7.印鑑
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 195.1KB)
国民健康保険療養費支給申請書見本 (PDFファイル: 237.7KB)
国民健康保険療養費請求兼領収書 (PDFファイル: 133.2KB)
次のようなものも支給できます。詳しくはお問合せください。
・治療費の全額を支払ったとき…旅行中、外出中、また急病などで緊急やむを得ない場合で、マイナンバーカード、資格確認書または保険証を持たずに診療を受けた医療費を全額支払った場合7割~8割を支給します。
・海外で受診したとき…一部払戻しがされる場合があります。
・マッサージ、はり、きゅうの施術…医師の同意が必要です。
・移送費…重病人の緊急の転院など移送に費用がかかった場合申請し、国保が認めたとき移送費が支給されます。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分(金額は旧ただし書き所得:注釈1) | 分類 | 3回目まで | 4回目以降 (多数該当:注釈3) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位所得者(901万円超え) | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||||||||||||
| 上位所得者(600万円超え901万円以下) | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||||||||||||
| 一般(210万円超え600万円以下) | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||||||||||
| 一般(210万円以下) | エ | 57,600円 | 44,400円 | ||||||||||||
| 住民税非課税世帯(注釈2) | オ | 35,400円 | 24,600円 | ||||||||||||
(注釈1) 旧ただし書き所得…総所得額-基礎控除額(原則43万円)
(注釈2) 住民税非課税世帯…世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
(注釈3) 多数該当…過去12か月以内に世帯内で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降は限度額が下がります。
- 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも医科・歯科と外来・入院は別計算となります。
- 世帯内で同月内に21,000円以上の自己負担が2回以上あった場合は合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療は対象外です。
| 所得区分(金額は課税所得) | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降(多数該当:注釈4) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 3(690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 現役並み所得者 2(380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 現役並み所得者 1(145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 一般 | 18,000円年間上限144,000円(注釈3) | 57,600円 | 44,000円 |
| 低所得者 2 (住民税非課税世帯:注釈1) |
8,000円 | 24,600円 | - |
| 低所得者 1 (注釈2) |
8,000円 | 15,000円 | - |
- 医療機関や医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療は対象外です。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
(注釈1) 住民税非課税世帯…世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
(注釈2) 世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の所得が、必要経費・控除(年金の所得は、控除を806,700円として計算)を差し引いたときに、0円となる人。なお、令和3年8月からは、各所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
(注釈3) 8月1日から翌年7月31日までの間の1年間について、年間上限144,000円
(注釈4) 多数該当…過去12か月以内に世帯内で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降は限度額が下がります。
限度額適用認定証
国民健康保険の被保険者が、入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を医療機関等で提示すると、窓口での自己負担額が限度額までとなります。
※限度額区分が「オ」または「低所得者2」の方が、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は長期入院該当となり、入院中の食事代が減額となります。マイナ保険証をご利用の方、ご利用でない方のどちらも、別途申請手続きが必要です。
※国民健康保険税に未納がある場合は、限度額適用認定証の交付及び窓口での支払の免除を受けることはできませんのでご注意ください。
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証を医療機関等で提示いただき、情報提供に同意することで、医療機関等で限度額区分の情報を確認することができ、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、保険の資格変更や税申請などの手続きをしてからマイナ保険証へ所得区分が反映されるまで、届出日から一定期間かかります。
そのため、手続き後すぐに医療機関等を受診された場合は、医療機関等で確認ができないことがあります。その場合には、医療機関等より伊東市保険年金課へ確認のお電話をいただければ、所得区分をお伝えすることができます。
マイナ保険証をご利用でない方
マイナ保険証をご利用でない方は、「限度額適用認定証」の申請をすると発行できます。
※70歳から74歳の限度額区分が「現役並み所得者3」または「一般」の方は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。医療機関等の窓口へ資格確認書を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
高額医療・高額介護合算制度
現在、健康保険の医療費が高額になった場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、介護保険にも同様の制度があります。しかし、それぞれについて申請し支給を受けても、医療の分と介護の分の自己負担の額を合わせてみると、その金額は大きくなることも少なくありません。そこで、健康保険と介護保険の自己負担額の合計額が年間の限度額を超えた場合は払戻しを申請できます。
出産育児一時金
出産1件につき500,000円を支給します。
ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関では488,000円となります。
葬祭費
死亡1件につき50,000円を支給します。
特定疾病療養費
血友病、人工透析の必要な慢性腎不全は、自己負担が10,000円となります。
ただし、70歳未満で慢性腎不全により人工透析を要する上位所得者については自己負担が20,000円となります。対象者は「特定疾病療養受療証」の申請をしてください。
マイナ保険証をご利用の方は、発行するものはありません。(マイナ保険証で特定疾病療養受療証の情報も確認することができます。)
マイナ保険証をご利用でない方は、「特定疾病療養受療証」を発行します。
入院時の食事代
入院中の食事に係る費用のうち一部(標準負担額)を、医療機関の窓口でお支払いいただきます。
負担額の軽減を受けるにはマイナ保険証の提示または保険年金課での申請が必要となります。
やむを得ない理由(※)で負担額の軽減を受けられず、軽減されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給の申請ができます。
(※やむを得ない理由とは、ひとり世帯の方が緊急入院をした場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。)
なお、この負担額は高額療養費制度の対象になりません。
| 所得区分(注釈1) | 標準負担額(1食あたり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) |
510円 |
||||||
| 住民税非課税世帯 低所得者 2 |
240円 【長期入院は190円:注釈2】 |
||||||
| 低所得者 1 | 110円 |
- (注釈1) 所得区分…上記「高額療養費」と同様
- (注釈2) 長期入院…過去12か月間の入院日数が90日超
療養病床入院時の食事代・居住費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食事代と居住費を医療機関の窓口でお支払いいただきます。
| 所得区分 (注釈1) |
医療区分 (注釈2) |
食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 1 | 510円 【一部医療機関では470円】 |
370円 | |||||||||
| 2・3 | 510円 【一部医療機関では470円、指定難病患者は300円】 |
370円 【指定難病患者は0円】 |
||||||||||
| 住民税非課税世帯 低所得者 2 |
1 | 240円 | 370円 | |||||||||
| 2・3 | 240円 【長期入院は190円:注釈3】 |
370円 【指定難病患者は0円】 |
||||||||||
| 低所得者 1 | 1 | 140円 | 370円 | |||||||||
| 2・3 | 110円 | 370円 【指定難病患者は0円】 |
||||||||||
- (注釈1) 所得区分…上記「高額療養費」と同様
- (注釈2) 医療区分…(2・3)厚生労働大臣が定める、入院医療の必要性の高い方 (1)2・3以外の方
- (注釈3) 長期入院…過去12か月間の入院日数が90日超
交通事故や暴力行為等にあったときは
交通事故や暴力行為、ペットによる噛みつきなど第三者(加害者)から受けた傷病でも国保で治療できます。
しかし、本来治療費は加害者が負担するべきものですが、国保が一時的に立て替えた後で加害者に請求します。国保を使用して治療を受ける際には届出が必要です。必ず事前に「傷病届等」の関係書類を提出してください。
また、示談を行う際には内容によって国保が使用できない場合がありますので、事前にご相談ください。
交通事故に関する届出様式は、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
介護サービスの利用
国保の被保険者で40歳から64歳の方が、脳血管障害等加齢による病気で介護や支援が必要と認められた場合、介護サービスが受けられます。
一部負担金の減免について
震災等で重大な損害を受けたときなど、一定の条件を満たせば一部負担金の減免が受けられます。
お問い合わせ先
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民健康保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する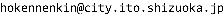










更新日:2024年06月01日